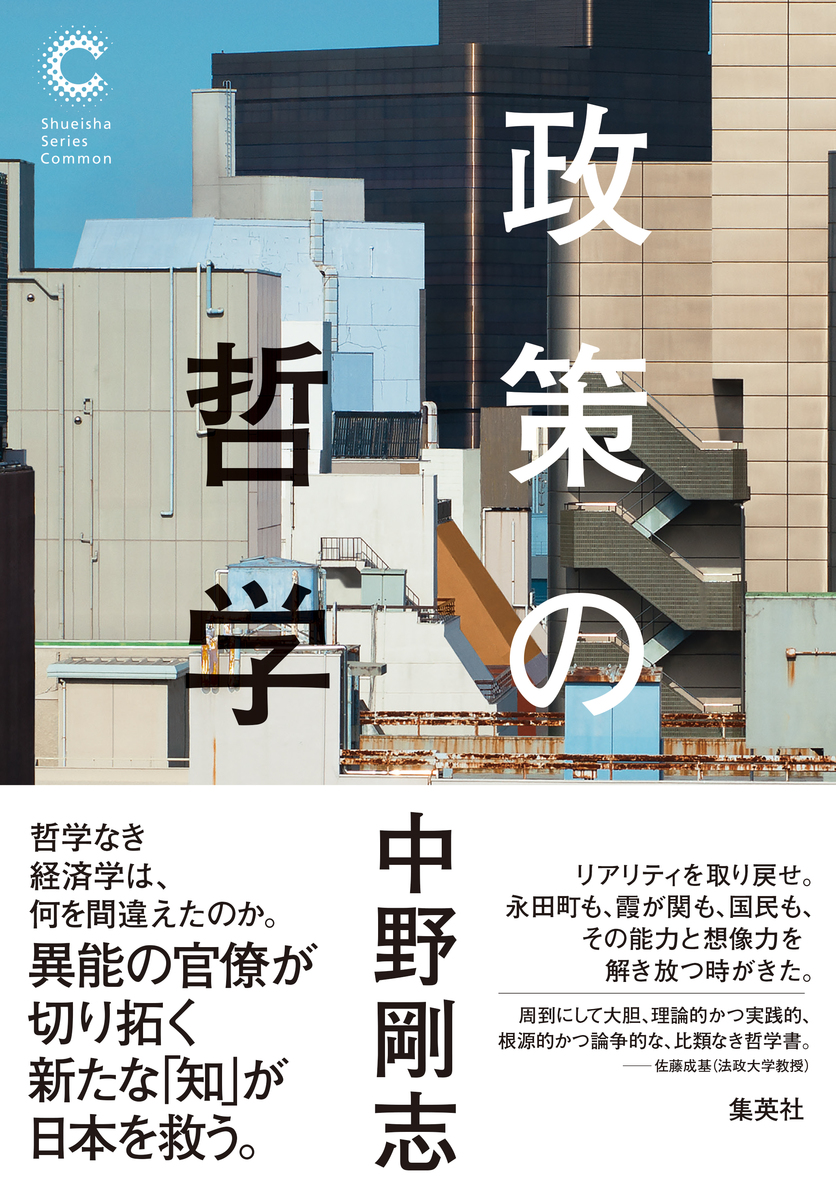書誌情報
集英社学芸単行本
政策の哲学(集英社シリーズ・コモン)
著者
あらすじ・概要
"■哲学なき経済学は、何を間違えたのか?
■異能の官僚が切り拓く、新たな「知」が日本を救う!
■絶賛!
周到にして大胆、理論的かつ実践的、
根源的かつ論争的な、比類なき哲学書。
――佐藤成基(法政大学教授)
【内容紹介】
なぜ世界経済は停滞し、どの国でも政治の不在を嘆く声が止まず、国家政策は機能していないのか――。
その理由は政策の世界で覇権を握っている主流派経済学の似非科学的なドグマにある。不確実性に満ちた世界で、とりわけ多中心性と複雑系によって特徴づけられる複合危機の時代において、社会の実在を無視した経済学に振りまわされた政策は毒でしかない。
そうした経済学の根源的・哲学的矛盾を衝き、新たな地平を切り拓くため、異能の官僚が批判的実在論を発展させた「公共政策の実在的理論」を展開する。
【著者プロフィール】
中野剛志 なかの・たけし (評論家)
1971年生まれ。東京大学教養学部卒業後、通商産業省(現・経済産業省)に入省。2003年にNations and Nationalism Prize受賞。2005年エディンバラ大学大学院より博士号取得(政治理論)。主な著書に『日本思想史新論』(ちくま新書、山本七平賞奨励賞)、『富国と強兵』(東洋経済新報社)、『TPP亡国論』(集英社新書)など。主な論文に‘Hegel’s Theory of Economic Nationalism: Political Economy in the Philosophy of Right’(European Journal of the History of Economic Thought), ‘Theorising Economic Nationalism’ ‘Alfred Marshall’s Economic Nationalism’(ともにNations and Nationalism), ‘“Let Your Science be Human”: Hume’s Economic Methodology’(Cambridge Journal of Economics), ‘A Critique of Held’s Cosmopolitan Democracy’(Contemporary Political Theory), ‘War and Strange Non-Death of Neoliberalism: The Military Foundations of Modern Economic Ideologies’(International Relations)など。"
序論
政策の科学は可能なのかを哲学する
科学哲学における存在論的転回の衝撃
ノーベル経済学賞受賞者たちの内部告発
主流派経済学は似非科学
羅針盤を持たない政策担当者
有権者全員が政策担当者
本書の構成
第一章 実証経済学とは何か
主流派経済学が使う非現実的な仮定
フリードマンによる主流派経済学の擁護
単純性と有益性の基準
非現実的な仮定の正当化
主流派経済学は実証主義なのか
フリードマンは道具主義者
観察の理論負荷性という問題
「抽象化」に関する誤解
「理念型」に関する誤解
仮説は単純かつ有益であるべき?
不確実性の問題
不確実性と方法論
貨幣を捨象した主流派経済学
フリードマンの方法論にすら背く主流派経済学
主流派経済学は科学ではない
第二章 科学とは何か
超越論的実在論
経験論と観念論への批判
認識的誤謬から生まれた相対主義
知覚と知覚される対象を区別する
開放系と閉鎖系
因果関係
現実世界の階層構造
階層と創発
DREIモデルの「遡及」とRRREモデルの「遡源」
遡及――深層の構造への移行
超越論的実在論の可謬主義
反基礎付け主義の傲慢
超越論的実在論と客観的真理
認識的相対主義
第三章 社会科学は可能なのか
批判的実在論
方法論的個人論の欠陥
個人論と集合論の止揚
マクロ経済学のミクロ的基礎は可能なのか
ルーカスによるケインズ経済学批判
「ルーカス批判」への批判
終末論的正当化
経済政策のミクロ的基礎の不在
構造と行為主体
社会活動の転換モデル
社会における創発
マクロ経済学とミクロ経済学
第四章 国家とは何か
理論と政策
批判的実在論・再論――社会的現実をいかにとらえるか
「位置」の理論
半・規則性
国家は行為主体なのか、社会構造なのか
国家行為者
下部構造的パワー
国家の下部構造的パワーの前提条件(1)――機能の多様性と自律性
創発するパワー
国家の下部構造的パワーの前提条件(2)――国家の「必要性」
国家の下部構造的パワーの前提条件(3)――領土化された集権性
「社会的創発」の理論
グローバリゼーション
国民国家の歴史社会学
国民国家の実在論的分析
ハーヴェイ・ロードの前提
公共選択理論の欠陥
公共選択理論の害
第五章 政策とは何か
「公共政策の実在論的理論」
存在論と政策手法
国家政策と実験
社会科学における遡及的推論
バスカーと複雑系理論との親和性
カオス理論との相違
ルールvs.裁量
第六章 ポスト批判的実在論
バスカーとポランニー
二人の類似性
科学の社会性
解釈とは内在化である
ポランニーのポスト批判的実在論
遡及と暗黙知
遡及についての相違
第七章 政策はどのように実行されるのか
批判的実在論はなぜ社会主義と結びつきやすいのか
人間の能力の限界
社会主義とケインズ主義
コロンブスの卵
ポスト批判的実在論とケインズ主義
特別に訓練された直観的裁量
ロウの道具的推論
道具的推論と暗黙知
一次的管理と二次的管理
期待
第八章 複雑系の世界における政策
リンドブロムの漸変主義
ポランニーの自生的秩序
多中心性
自由と伝統
ブルーミントン学派
ケインズと多中心性
多中心性と実在論
複雑系理論と公共政策
経路依存性
アジャイルな政策形成
「長期的には、皆、死んでしまうのだ」
リカードとマルサスの論争
マルサスとケインズ
第九章 財政哲学
財政政策を実在論的理論で考える
主流派経済学の商品貨幣論
商品貨幣論の欠陥
信用貨幣論――借用書としての貨幣
政府の負債
貨幣創造
信用貨幣論の実在論的基礎(1)――社会関係
信用貨幣論の実在論的基礎(2)――「創発」による信用創造
貨幣経済の多中心性
ラーナーの「機能的財政」論
インフレーション
財政金融政策だけではインフレーションは起きない
インフレーションの実在論的分析
道具的推論と機能的財政
ミンスキーによる機能的財政論の修正
修正機能的財政の実在論的分析
粗調整と微調整
「裁量」再論
科学としての現代貨幣理論
第十章 政治とは何か
人間と裁量
民主政治――政治的共同体の必要性
国民国家とは何か
裁量の限界
脱政治化
脱政治化の三つの戦術
脱政治化の問題点
グローバリゼーションという脱政治化
自己実現的予言
結論
政策の可能性
社会科学の方法論
バビロン的思考様態
証拠に基づく政策立案
複合危機
二十一世紀の政策哲学
註